不動産登記に関連する具体的な事例を多角的に列挙し、各テーマごとに詳細に解説いたします。これらの事例は、過去の試験問題や実務上のケースを参考にしています。
🏠 表題登記・表示登記に関する具体的事例
1. 新築建物の表題登記申請における平面図の添付漏れ
- 事例: 新築した建物の表題登記申請を行ったが、平面図が添付されていなかった。登記官は受理を拒否し、所有者は再度平面図を添付して申請する必要があった。
- 解説: 表題登記には、建物の構造や形状を示す平面図の添付が必要です。これにより、建物の現況が正確に公示されます。
2. 増築後の表題登記申請における現況図の寸法誤差
- 事例: 増築後の表題登記申請で提出された現況図に寸法誤差があり、登記官から修正を求められた。所有者は修正図面を提出し、再申請を行った。
- 解説: 増築後の建物の現況を正確に反映するためには、寸法の誤差がないように現況図を作成する必要があります。
3. 共有建物の表題登記申請における共有者間の合意不足
- 事例: 共有建物の表題登記申請を行う際、共有者間で合意が得られず、登記申請が遅延した。最終的に、共有者全員の同意を得て申請が完了した。
- 解説: 共有建物の登記申請には、共有者全員の同意が必要です。合意形成のプロセスが重要となります。
🏘️ 境界確定・物権・相隣関係に関する具体的事例
1. 隣接土地の通行権の認定
- 事例: 隣接土地の所有者が、自らの土地を通行するための通行権を主張したが、通行の必要性が認められず、通行権は認められなかった。
- 解説: 通行権は、土地の利用に必要な場合に認められますが、その必要性が証明されなければ認められません。
2. 境界標の設置に関する判例の適用
- 事例: 隣接地所有者間で境界標の設置を巡る争いがあり、判例に基づき、境界標の設置が適法であると認定された。
- 解説: 境界標の設置は、隣接地所有者間の合意や判例に基づいて行われます。
🧾 取得時効・占有に関する具体的事例
1. 10年の時効取得の条件
- 事例: 他人の土地を10年間、平穏・公然・継続して占有していたが、所有権の取得は認められなかった。
- 解説: 時効取得には、占有が平穏・公然・継続して行われていることが必要です。
2. 善意・悪意による時効取得の違い
- 事例: 善意で他人の土地を占有していたが、悪意で占有していた場合、時効取得が認められなかった。
- 解説: 善意・悪意によって、時効取得の可否や期間が異なります。
🏘️ 共有土地・分割に関する具体的事例
1. 共有土地の分割請求の可否
- 事例: 共有土地の分割請求を行ったが、共有者全員の同意が得られず、分割が認められなかった。
- 解説: 共有土地の分割には、共有者全員の同意が必要です。
2. 管理行為の単独可否
- 事例: 共有土地の管理行為を単独で行ったが、他の共有者から異議が出て、管理行為が無効とされた。
- 解説: 管理行為は、共有者の過半数の同意で行うことができます。
📄 契約・意思表示の無効・取消に関する具体的事例
1. 錯誤や詐欺に基づく契約無効
- 事例: 錯誤や詐欺に基づく契約が無効とされ、境界協定書や売買契約書の法的効力が問われた。
- 解説: 契約の無効を主張するには、錯誤や詐欺の事実を証明する必要があります。
🏛️ 物権変動に関する具体的事例
1. 表題登記前後の権利移動
- 事例: 表題登記前に権利が移動したが、登記が完了する前に権利が移動した場合、権利の成立に影響を与えることがある。
- 解説: 登記は権利の公示手段として重要な役割を果たします。
2. 登記簿上の権利と現況の不一致
- 事例: 登記簿上の権利と現況が不一致の場合、権利関係の確認や修正が必要となることがある。
- 解説: 不一致の解消には、関係者間での協議や手続きが重要です。
- 土地家屋調査士

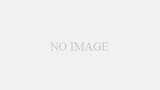
コメント