過去のケースだけで判断すると、現状や今後の不動産市場の動向によるズレが生じる場合があります。
不動産鑑定士の判断力・補正力を養う際には、時代背景や市場変化を意識することが重要です。以下、多角的・多面的に整理します。
1. 過去ケースと現在・将来の違いの例
| 分野 | 過去ケースの傾向 | 現状・今後の変化 | 鑑定に与える影響 |
|---|---|---|---|
| 地価・土地価格 | 緩やかな上昇や安定、取引事例の豊富さ | 地価高騰、都市部の急激な上昇、人気エリア集中 | 過去事例の補正値が参考にならない場合あり。取引事例比較法の精度低下 |
| 投資物件 | 国内投資家主体、融資条件も標準化 | 外資・機関投資家の参入増、低金利・高倍率融資 | 収益還元法での利回り設定や期待キャッシュフローの補正が必要 |
| 市場流動性 | 取引件数が豊富で参考事例多数 | 流動性低下・取引件数減少、一部エリアのみ活発 | 類似物件の抽出が困難、補正幅が広くなる |
| 法規・制度 | 過去の用途地域・固定資産税制度で補正 | 新規都市計画、税制改正、建築規制変更 | 補正計算や原価法に影響、現地調査の重要性増 |
| 社会・経済要因 | 過去の景気サイクルに準じた賃料水準 | インフレ・人口減少・テレワーク普及 | 収益還元法・賃料想定の補正が必要 |
2. 判断・補正・説明に与える具体的影響
- 補正幅の再評価
- 過去事例の価格や利回りをそのまま使うと、現在の市場実勢と乖離する
- 例:地価高騰エリアでは過去比+20~30%補正が必要な場合も
- AI結果の精査
- AIや過去データに基づく計算結果は、現状の市場動向を完全には反映できない
- 例:外資参入により、オフィス賃料の予測値が過去事例より高くなる可能性
- 説明力の重要性増加
- 過去事例との差異をクライアントや行政に論理的に説明する必要がある
- 例:「過去類似事例より駅近立地で賃料上昇率が高く、補正を加えました」
- ケーススタディ学習の補正
- 過去ケースをそのまま学ぶだけでなく、「現状市場条件を反映した仮想修正版」を作り、判断練習に活かす
3. 学習・実務対応の具体策
- 過去事例+現状データの組み合わせ
- 公示地価、路線価、取引価格速報、賃料動向など最新データと組み合わせる
- シナリオ分析
- 地価高騰や外資参入など、複数の市場変化シナリオを想定して評価書を作成
- 先輩鑑定士レビュー
- 過去の評価手法と現状補正の妥当性を、先輩とディスカッション
- AIツールの活用
- 過去事例+最新データを学習させるAIで、より現状に沿った計算結果を取得
💡 まとめ
- 過去ケースは基礎学習に有効だが、現在・将来の市場変化(地価高騰、外資参入、人口減少など)を必ず加味することが重要
- 判断・補正・説明の力は、過去事例だけでなく現状・未来予測も組み合わせて鍛える必要がある
- AIやツールは便利だが、現状との乖離を判断し補正するのは人間の役割

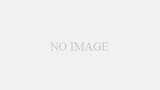
コメント