「不動産鑑定士の仕事が『計算・整理』から『判断・補正・説明』に重点が移る時、どうすれば良いか」です。
1. 判断力を高める
a. データの妥当性チェック力
- 収益還元法・原価法・取引事例比較法でAIやツールが計算した結果を、盲目的に信じず確認する
- 具体例
- AIのDCF計算結果が市場利回りと乖離していないかチェック
- 減価補正の値が過去事例と大きく違わないか比較
b. 権利関係・現地状況の判断力
- 公共事業や相続案件では、土地・建物の権利関係や現場の特殊条件が複雑
- 具体例
- 建ぺい率・用途制限・私道負担の有無などがAIの自動評価では考慮されない場合、手作業で判断
- 過去の取引事例では扱われない特殊条件(斜面地・高低差など)を考慮
c. 補正判断力
- 比較事例から価格補正を行う際、AIの自動補正を最終的に調整
- 具体例
- 「類似物件より駐車場が少ない → 価格補正」
- 「立地が駅から遠い → 減価補正」
2. 説明力・報告力を磨く
a. 報告書作成力
- AIが作るドラフトをそのまま提出せず、論理的に補足
- 具体例
- 市場動向の解説
- 権利関係の特記事項
- 取引事例の選定理由
b. クライアント・行政との説明力
- 売買:投資家や一般顧客に説明
- 相続:税務署や関係者に客観性を示す
- 公共事業:行政や補償関係者への説明
- 具体例
- 「AIが計算したDCF結果ですが、○○の前提条件を補正しています」
- 「原価法の建物減価補正は、現地調査結果を反映させました」
3. ツール+AI活用力を磨く
- AIの結果を鵜呑みにせず、自分の判断・補正に結び付ける力が必要
- 具体例
- Excelマクロで自動計算された収益還元法の値を、過去類似案件と比較し、補正値を決定
- GISで抽出された土地境界を現地で確認し、修正
- ポイント
- ツール操作は最小限の時間で、判断・補正・説明に集中する
4. 実務経験を積む
- 案件の種類や量を経験するほど、「AIの結果と現実のズレ」を把握できる
- 具体例
- 売買案件10件経験 → 収益還元法の典型値と市場乖離の傾向が分かる
- 公共事業案件5件経験 → 権利関係や補償計算の特殊事例に慣れる
5. 学習・訓練
- ケーススタディ学習:過去の複雑案件を分析して、補正・判断の流れを学ぶ
- ロールプレイ:クライアント説明・行政対応を想定して練習
- レビュー・フィードバック:上級者や先輩鑑定士の判断プロセスを観察・議論
6. まとめ:具体的行動指針
- AI計算を正しく理解・チェックする
- 盲信せず、入力条件・結果の妥当性確認
- 補正・判断に慣れる
- 現地調査や権利関係情報を踏まえて調整
- 説明・報告力を鍛える
- 数字だけでなく背景・理由を説明できる
- 経験の量で精度向上
- 案件タイプ別に経験を積む
- 学習+レビュー
- ケーススタディと先輩鑑定士のレビューで判断力を養う
- ツール+AIを効率的に活用
- 単純作業はAI任せ、判断・補正・説明に集中
💡 ポイント
- 「計算・整理」はAIが補助する
- 人間は「判断・補正・説明」に集中する
- 経験・ケース学習・ツール活用の3つを組み合わせると、専門性と効率が飛躍的に向上

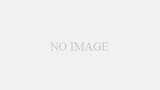
コメント