不動産鑑定の実務で重視される要素と案件特性から逆算して設定したものです。詳細に解説します。
1️⃣ 根拠の考え方
不動産鑑定では、どの手法が評価対象物件や案件目的に対して妥当性を持つかによって使用比率が変わります。
比率は以下の要素から算出・目安化しています。
① 案件タイプの目的
| 案件タイプ | 主な目的 | 手法優先度の方向性 |
|---|---|---|
| 売買 | 市場価格や投資価値算定、交渉材料 | 収益還元法(賃貸収益物件)、取引事例比較法(市場価格反映)を重視 |
| 相続・贈与 | 税務申告用の客観評価、権利整理 | 原価法(建物評価)重視、収益還元法・比較法は補助的に使用 |
| 公共事業 | 用地取得・補償、公的報告 | 原価法(建物再取得・補償費算定)を中心、比較法で土地価値を補正 |
② 手法の特性
| 手法 | 特性 | 使用割合への影響 |
|---|---|---|
| 収益還元法 | 賃貸収益・利回りから価値を算定 | 賃貸物件が多い売買案件では比重が高い(40%程度) |
| 原価法 | 建物の再取得費+減価修正で評価 | 公共事業や特殊建物、相続物件では比重が高い(40~60%) |
| 取引事例比較法 | 類似物件との比較で市場価値を反映 | 市場価格重視の売買、公共用地の土地評価で使用(30~40%) |
③ 実務経験・傾向
- 売買案件:賃貸ビルや投資用不動産の場合、収益還元法が実務上最も説得力がある → 40%
- 相続案件:建物の再建築費をベースに評価することが多く、原価法の比重が高め → 40%
- 公共事業:補償対象の建物や土地を客観的に評価する必要がある → 原価法60%、比較法40%でバランス
④ 作業時間・工数との連動
- 評価手法ごとの計算・補正作業時間も比率に反映
- 例:
- 売買案件:収益還元法計算・比較法補正が多く、原価法は簡易チェック程度 → 40:40:20
- 相続案件:建物評価に時間がかかる → 原価法40%、他手法30%ずつ
- 公共事業:建物移転費・補償算定が中心 → 原価法60%、土地比較補正40%
⑤ 補正・総合評価で調整
- 実務では最終的に総合評価で加重平均を取るため、手法割合はあくまで計算工数・重点度の目安
- 案件によって変動可能:
- 小規模土地売買 → 比較法70%、収益還元法0%
- 高稼働賃貸ビル → 収益還元法50%、比較法30%、原価法20%
💡 まとめ
- 使用割合は「案件特性 × 手法特性 × 計算工数の目安」から設定
- 絶対値ではなく、業務の重点配分や計算時間の目安として理解するのが正しい
- 実務では物件種別・案件目的・依頼者要望で柔軟に調整

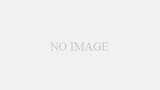
コメント