不動産鑑定士が作成する鑑定評価書は、主に 収益還元法・原価法・取引事例比較法 の3つの手法を用いて価値を算定します。
ここでは多角的・多面的・詳細具体的に列挙して解説します。
1️⃣ 鑑定評価書の全体構成(概略)
評価書は以下の流れで構成されます。
- 表紙・概要
- 物件名称、所在地、鑑定評価日、依頼者名
- 依頼目的と条件
- 例:相続評価、売買参考、担保評価、企業財務用
- 権利関係(所有権・借地権・地上権など)
- 物件概要
- 土地・建物の面積、形状、地形、用途地域、建築年、構造
- 現地調査・資料調査
- 公示地価、地価調査、固定資産税評価額、取引事例
- 評価方法の選定理由
- 収益性重視か、原価重視か、比較事例重視か
- 各手法による評価
- 収益還元法
- 原価法
- 取引事例比較法
- 総合評価
- 各手法を加重平均・調整して最終評価額を算定
- 付記・参考資料
- 計算式、図表、写真、参考文献
2️⃣ 収益還元法
目的:投資収益をもとに不動産価値を算定
手順と具体内容
- 将来収益の予測
- 賃料、稼働率、管理費・修繕費を調査
- 例:月額賃料100万円 × 年12か月 × 稼働率95%
- 純収益(NOI)算定
- 総収入 − 運営費・固定費
- 還元利回り(資本化率)の設定
- 市場利回り・リスクプレミアムから算定
- 価値算定
- 不動産価値 = 純収益 ÷ 還元利回り
多角的ポイント
- 賃貸市場分析:近隣物件の賃料相場・空室率
- 物件特性調整:築年数、建物構造、立地の優劣
- リスク評価:景気変動、契約条件、法規制
- DCF法(詳細):将来キャッシュフローを割引現在価値に換算
3️⃣ 原価法(積算法)
目的:建物再取得コスト+土地価値をベースに算定
手順と具体内容
- 土地価値の算定
- 公示地価・固定資産税評価額・取引事例から推定
- 建物の再取得原価
- 建築費 × 延床面積
- 経年減価(築年数・耐用年数)を控除
- 合計
- 土地価値 + 減価後建物価値 = 不動産価値
多角的ポイント
- 建築単価の変動:地域・仕様による単価差
- 減価の種類:物理的劣化、機能的陳腐化、経済的陳腐化
- 土地の形状・接道条件:再建築可能性や利用制限の影響
- 公共制限:容積率・建ぺい率・都市計画制限
4️⃣ 取引事例比較法
目的:類似物件の実際取引価格をもとに評価
手順と具体内容
- 事例収集
- 近隣類似地・類似建物の取引事例(売買価格、面積、築年数)
- 事例の調整
- 土地形状、用途地域、面積、道路付、築年数などの差を加減
- 平均化・評価
- 調整後価格を参考に評価対象物件の価値を算定
多角的ポイント
- 市場動向把握:過去1〜2年の取引価格トレンド
- 調整精度:細かい物件特性の差を金額に反映
- 希少性・立地優劣:交通利便性、商業施設近接、景観など
- 補正手法:単純比例補正、価格指数、係数補正
5️⃣ 鑑定士としての判断・総合評価
- 各手法の結果を単純平均ではなく加重平均や調整して最終評価額を決定
- 評価書には必ず根拠の明示:
- 調査方法
- 計算式
- 使用資料・公示地価・取引事例
6️⃣ 多面的ポイント(作業上の注意)
- 法的側面:所有権、借地権、都市計画制限、税務関連
- 経済的側面:市場動向、景気・金利変動、地域経済
- 技術的側面:建物構造、耐用年数、修繕履歴
- 社会的側面:地域開発計画、交通・インフラ整備、周辺環境
- 倫理・透明性:依頼者への説明責任、鑑定士法・倫理規定遵守

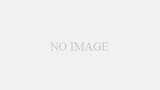
コメント