不動産鑑定士試験は、国土交通省所管の国家試験で
「一次(短答式)」「二次(論文式)」「三次(口述試験)」の三段階から成ります。
以下では科目・出題形式・評価ポイント・学習戦略などを多角的に詳しくまとめます。
1️⃣ 全体像
| 区分 | 実施時期(例) | 主な目的 | 合格率(目安) |
|---|---|---|---|
| 一次:短答式 | 5月 | 経済学・会計学の基礎学力を確認 | 25〜35% |
| 二次:論文式 | 8月 | 不動産評価に必要な専門知識・応用力を確認 | 15〜20% |
| 三次:口述式 | 10月 | 実務適性・表現力を確認 | ほぼ全員(合格率95%以上) |
2️⃣ 一次試験(短答式)
目的:経済学・会計学の基本的素養を測る
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 科目 | 経済学、会計学(各50点満点) |
| 形式 | 四肢択一マークシート |
| 試験時間 | 経済学2時間/会計学2時間 |
| 合格基準 | 各科目40%以上かつ総得点65%前後 |
| 出題範囲 | 〈経済学〉ミクロ・マクロ・計量・財政金融等 〈会計学〉簿記・財務諸表・企業会計基準 |
💡ポイント
- 経済は大学1〜2年レベル、会計は日商簿記2級〜1級の範囲。
- 短答式の合格は翌年以降2年間有効。
3️⃣ 二次試験(論文式)
目的:不動産鑑定評価に必要な専門知識・分析力を総合的に問う最難関
| 科目 | 試験時間 | 概要 |
|---|---|---|
| 鑑定理論(短答+記述) | 計3時間 | 不動産鑑定評価基準・法規・手法(原価・比較・収益)を総合的に論述 |
| 鑑定理論(演習) | 2時間 | 実際の評価書作成を想定し、事例計算や記述 |
| 民法 | 2時間 | 物権・債権・相続・借地借家・担保権など不動産取引関連 |
| 経済学 | 2時間 | マクロ・ミクロの応用、都市経済、地価変動要因 |
| 会計学 | 2時間 | 企業財務分析、DCF法に必要な会計知識 |
| 不動産関連科目(選択) | 2時間 | 建築学 or 土地利用計画など選択式 |
特徴:
- 記述量が多く、論理的な文章構成・計算精度・法的根拠の明示が重視。
- 合格率は15〜20%程度。一次合格者でも数年かけて挑戦する人が多い。
4️⃣ 三次試験(口述式)
- 二次合格者対象。
- 面接官2〜3名による個別面接(約10〜15分)。
- 内容:鑑定理論・実務対応・職業倫理。
- 「受験者が基本的知識を持ち、鑑定士としての態度があるか」を確認。
- 合格率95%以上。
5️⃣ 受験・登録までの流れ
- 受験申込:毎年2〜3月頃。
- 一次(5月)→二次(8月)→三次(10月)。
- 合格後、**実務修習(1年程度・レポート提出)**を終えて登録。
- ここで初めて「不動産鑑定士」と名乗れる。
6️⃣ 学習期間と目安
- 初学者:2〜3年(短答1年+論文1〜2年)
- 必要学習時間:約2,500〜3,500時間。
- 予備校(TAC・LEC等)利用が主流。
7️⃣ 出題の多面的特徴
- 法律 × 経済 × 会計 × 建築・都市計画が交差する総合試験。
- 数字計算(収益還元法・DCF法)と論述の両方を問う。
- 不動産市況や制度改正(民法改正、固定資産税評価など)にも敏感。
8️⃣ 合格後の実務修習
- 不動産鑑定士協会連合会が主催。
- eラーニング+集合研修+実地演習。
- 修了試験(口頭試問)を経て正式登録。
9️⃣ 受験料・その他
- 一次:13,000円前後
- 二次:26,000円前後
- 三次:13,000円前後(年度で微変動)
- 予備校費用:総額100〜150万円程度が一般的。
✅まとめ
不動産鑑定士試験は
経済学・会計学の基礎 → 鑑定理論・法務・都市計画までを総合的に問う、記述重視の三段階国家試験。
- 学歴不問だが大学レベルの知識+長期計画的学習が必須。
- 合格後は1年程度の実務修習を経て登録し、初めてプロとして活動できます。
- 不動産鑑定士

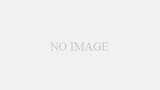
コメント