ミシュラン評価でよく聞かれる疑問で、非常に重要なポイントです。結論から言うと、個人の好みや味覚に左右されないよう、複数の工夫が徹底されています。多角的に整理します。
1. 味覚の偏りを防ぐ仕組み
- 統一された評価基準
- 味覚・調理技術・盛り付け・サービス・価格の5項目など、項目ごとに具体的な評価基準が定められている
- 「好み」ではなく、あくまで基準に沿って採点
- 匿名・個人評価の複数回確認
- 1回の訪問で決めず、複数回の来店や別インスペクターの評価と照合
- これにより、個人の偏った味覚の影響を減らす
- シニア・上司によるレビュー
- 評価報告書は上司やシニアが確認
- 異常な偏りや極端な感想がないかチェック
- 訓練された味覚
- インスペクターは採用後、一定期間のトレーニングで「標準的な味覚・評価感覚」を身につける
- 個人の好みではなく、ミシュラン基準での判断ができるように訓練される
2. 評価プロセスによる公平性確保
- 複数インスペクターの独立評価
- 高級店・★★★店では複数のインスペクターが異なる日や時間帯に訪問
- 個人の好みによる偏りを平均化
- 報告書統合・格付け決定
- 本社で複数報告書を統合して★★★~★1、ビブグルマンなどに格付け
- 個人の好みではなく、客観的な評価に基づく格付け
3. ポイントまとめ
- インスペクター個人の味覚に完全に依存するわけではない
- 統一された評価基準と訓練、複数回訪問・複数インスペクター評価、報告書レビューで偏りを補正
- 最終格付けは本社で統合され、個人の好みは最小化
要するに、インスペクターの好みや味覚が左右することはある程度避けられませんが、ミシュランでは多重のチェックと基準化で公平性を高め、最終格付けには個人の好みをほぼ反映させない仕組みになっています。

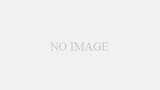
コメント